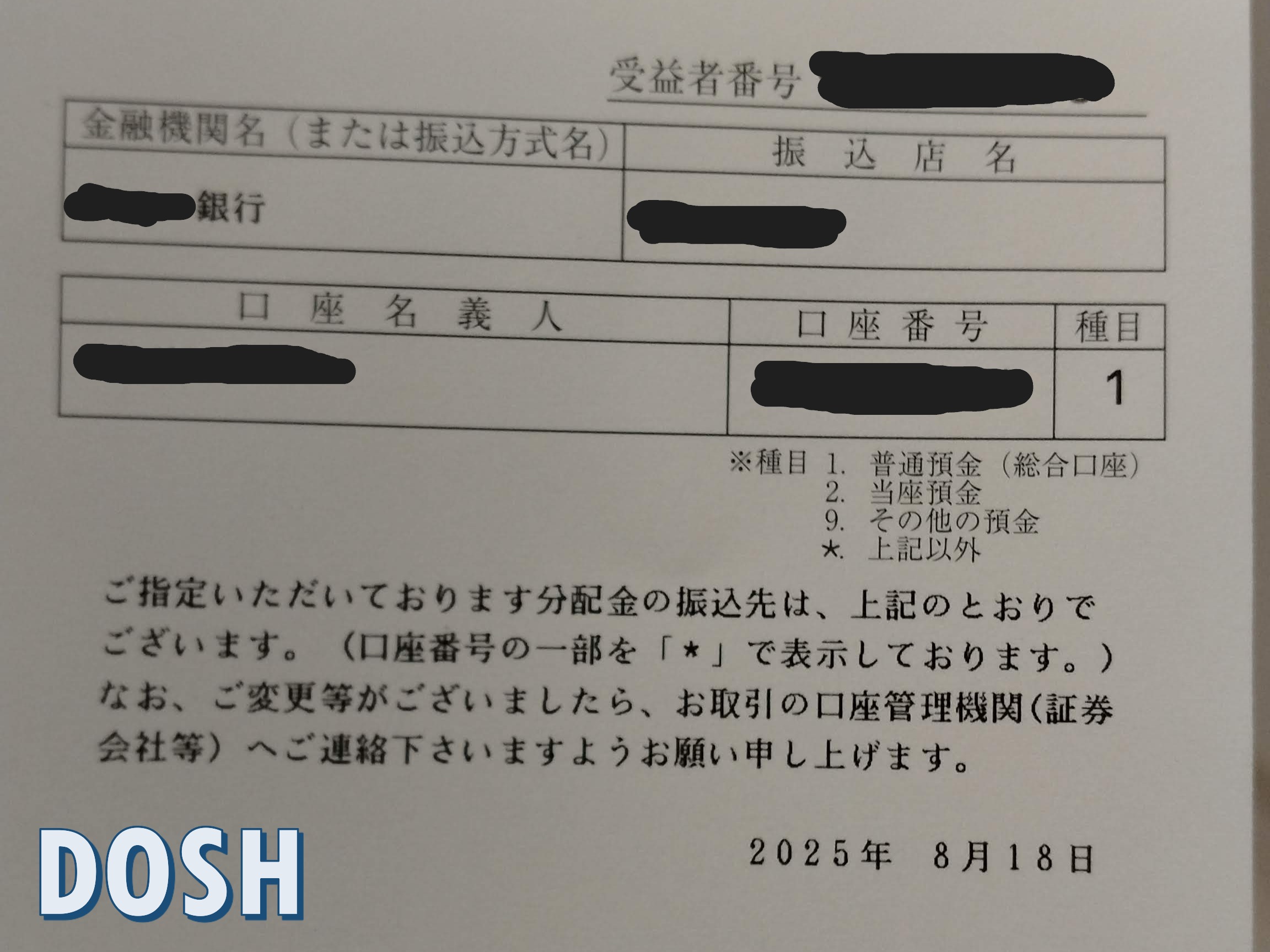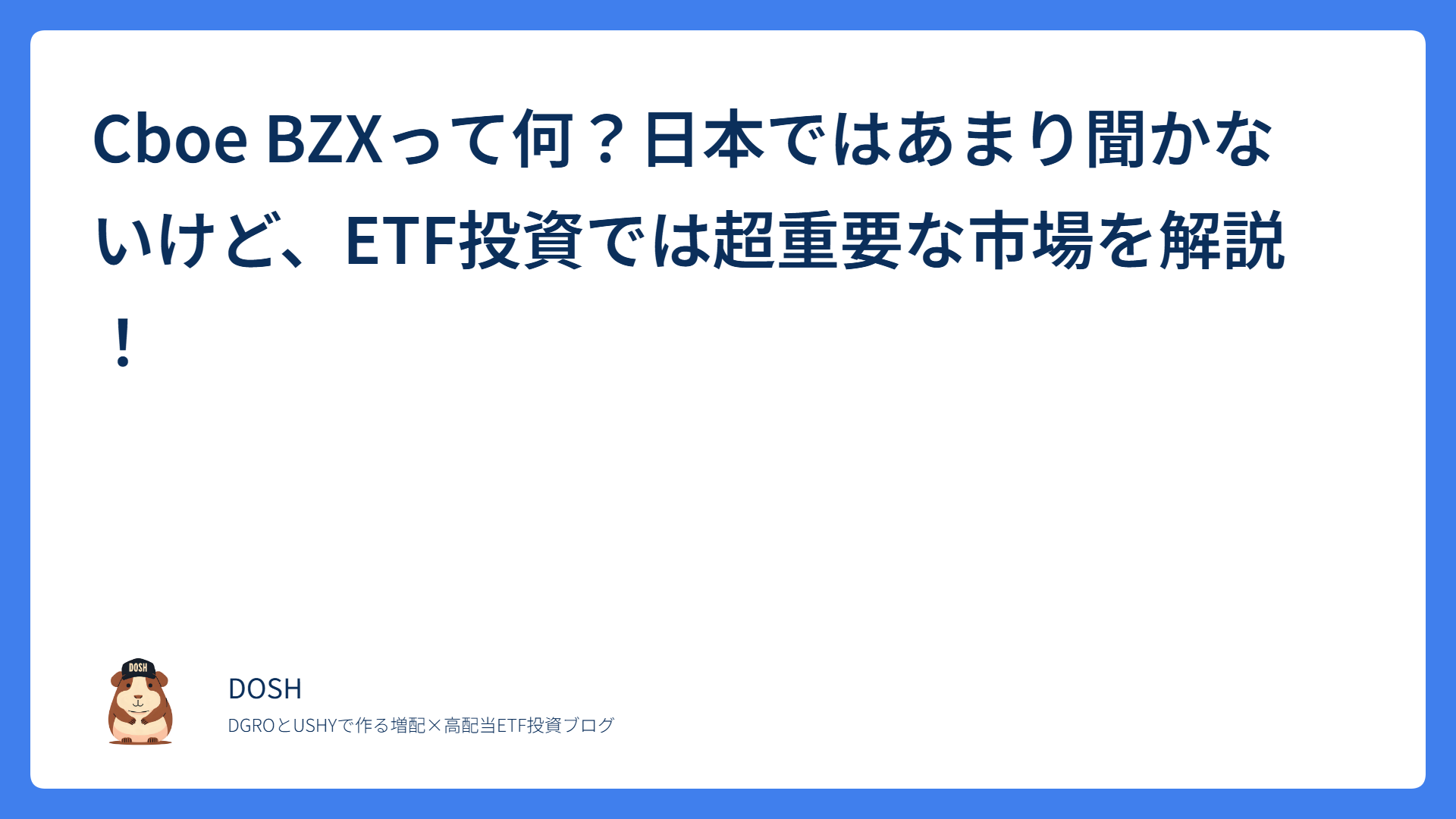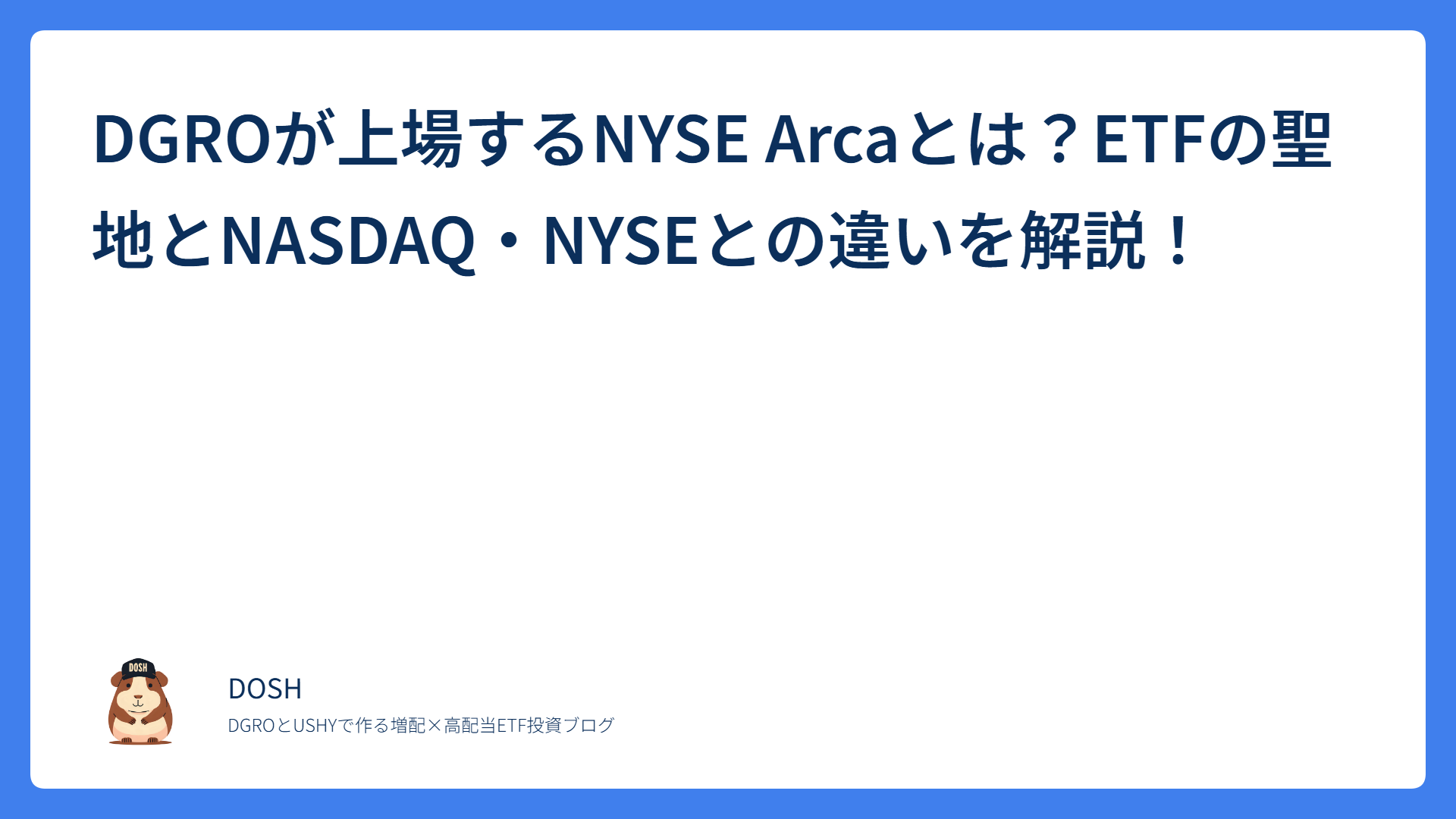【投資知識シリーズ】USHYの裏側を支える世界三大格付け会社とは?
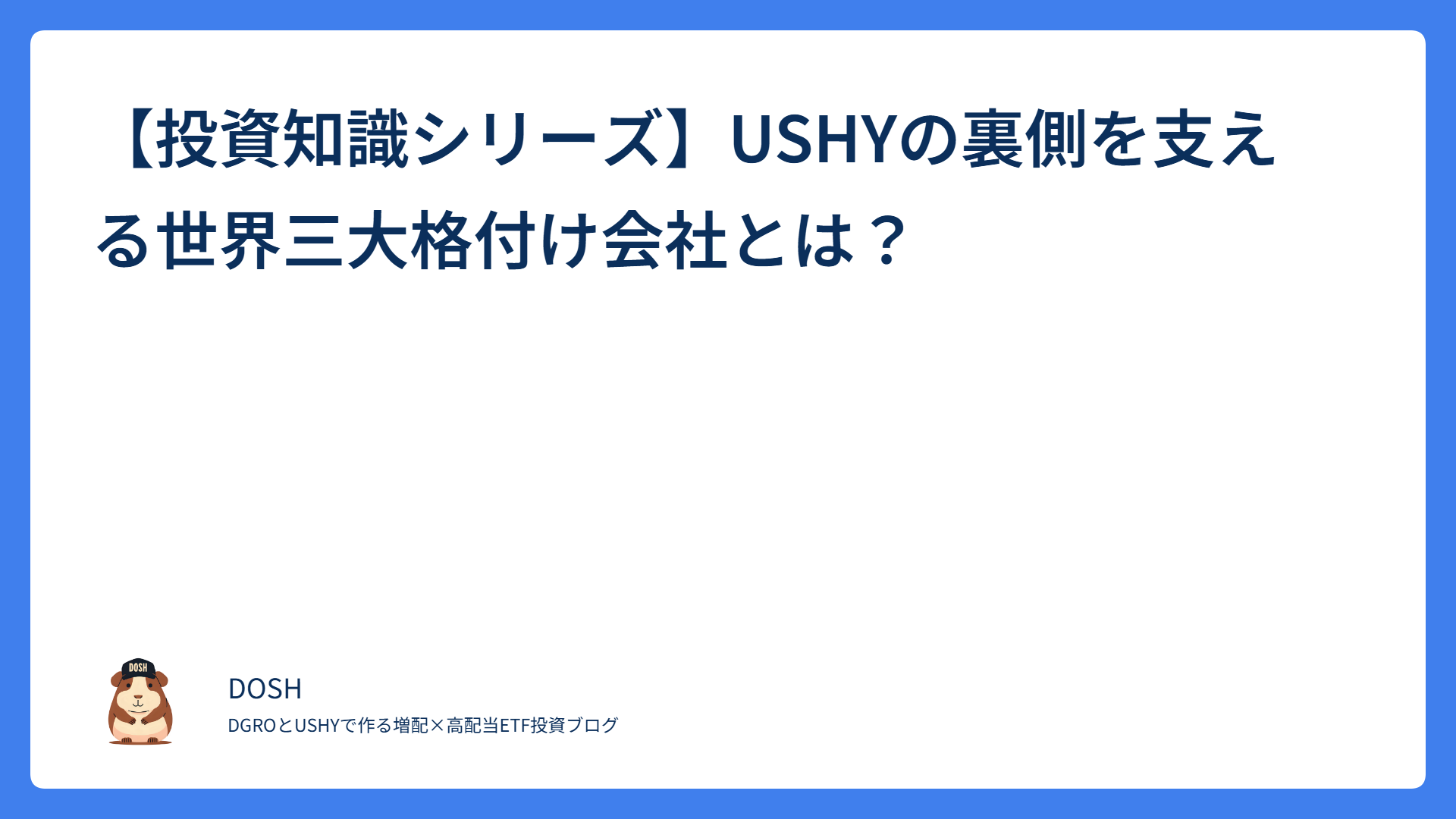
はじめに:当ブログとDOSH戦略
当ブログでは、米国ETFを活用した独自の長期投資法、DOSH戦略をご紹介しています。
この2本を軸に、「育つ配当」と「安定した不労所得」のバランスを調整し、長期的なインカムを築く投資法です。
今回はその“高利回り担当”である2258(iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF、米国ETFではUSHY)の裏側に迫る投資知識シリーズ。
「ハイイールド債の格付けってどう決まるの?」
「誰が判断しているの?」
この疑問に答えるため、世界の債券市場を支える三大格付け会社をご紹介します。
USHYのハイイールド債と格付けの重要性
USHYは、ICE BofA U.S. High Yield Constrained Indexに連動し、米国内市場で流通する米ドル建てハイイールド社債に投資します。
ここでいう「ハイイールド債」とは、投資適格(BBB-/Baa3以上)未満の格付けが付与された社債のこと。
なぜ格付けが重要かというと…
- 投資家にとっての信用リスクの目安になる
- ETFの組入基準に格付け条件が含まれている
- 価格変動(スプレッド)にも大きく影響する
USHYも、一定以上の流動性と信用格付けを持つハイイールド債に分散投資しており、その根拠となるのが格付け会社の評価です。
世界三大格付け会社とは?
では、その格付けを誰が行っているのでしょうか?
世界の債券市場で基準となっているのが、**ムーディーズ(Moody’s)、S&Pグローバル(S&P Global Ratings)、フィッチ(Fitch Ratings)**の3社です。
ムーディーズ(Moody’s Investors Service)
1909年創業、米ニューヨーク本社。
世界で最も影響力のある信用格付機関のひとつで、米国債・社債・証券化商品・国際機関債まで幅広い分野をカバーしています。
格付表記は「Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B…」と続き、投資適格と投機的等級の境界はBaa3/以下。
リーマンショック後は評価手法の厳格化を進め、ESG評価を含めた企業の総合的リスク評価にも力を入れています。
S&Pグローバル(S&P Global Ratings)
1860年設立、世界最大級の金融情報企業S&P Globalの格付部門。
「AAA、AA、A、BBB、BB、B…」の表記で知られ、特に**BBB-/BB+**が「投資適格」と「ハイイールド」の分かれ目とされています。
国債、社債、地方債など幅広い発行体を評価し、世界中の機関投資家がベンチマークに使用。
市場インデックスS&P500の運営会社でもあるため、資本市場との連動性が非常に高いのが特徴です。
フィッチ(Fitch Ratings)
1914年創業、ロンドンとニューヨークを拠点とする国際格付け会社。
規模ではムーディーズやS&Pに劣りますが、欧州債券・新興国市場での格付けに強く、国際金融機関・各国中央銀行からの信頼も厚いです。
ESG要素を組み込んだ信用評価モデルをいち早く導入するなど、近年ではグローバルな影響力を拡大しています。
ハイイールド判定とUSHYへの組入れ
これら三大機関の格付を基に、「投資適格」か「ハイイールド」かが判断されます。
例えば…
- S&Pが「BB+」、Moody’sが「Ba1」と評価した場合=投機的等級(ハイイールド)
- 複数社の評価を総合して基準を満たせばUSHYに組入れ可能
つまり、USHYは「米国市場に流通する信用度中~低めの社債」に広く投資し、利回りを高めているのです。
日本との格付けの違いと楽天の例
以前の記事(【USHY組入社債発行企業紹介】楽天グループがなぜハイイールド?)で紹介した通り、
米国格付けでは「投機的等級」とされる一方、日本の格付機関(R&I、JCRなど)は「A格相当」と評価することがあります。
これは、
- 日本機関は金融子会社の基盤やグループ支援を重視
- 米国機関は連結全体の負債水準や競争環境をより厳格に評価
という評価軸の違いによるもの。
この違いを理解しておくと、「なぜこの企業がハイイールド扱い?」という疑問にも納得感が出ます。
まとめ:格付けは投資の“共通言語”
USHYのようなハイイールドETFの裏には、**三大格付け機関の評価という“共通言語”**があります。
どの国のどの企業の債券でも、格付けがあることで投資判断がしやすくなるのです。
DOSH戦略においても、この「信用リスクの見える化」があるからこそ、2258を通じて安心して高利回りインカムを受け取ることができます。
今後は、USHYの理解をより深めるために格付けの読み方や「投資適格との境界線」について掘り下げていこうと思います。お楽しみに!