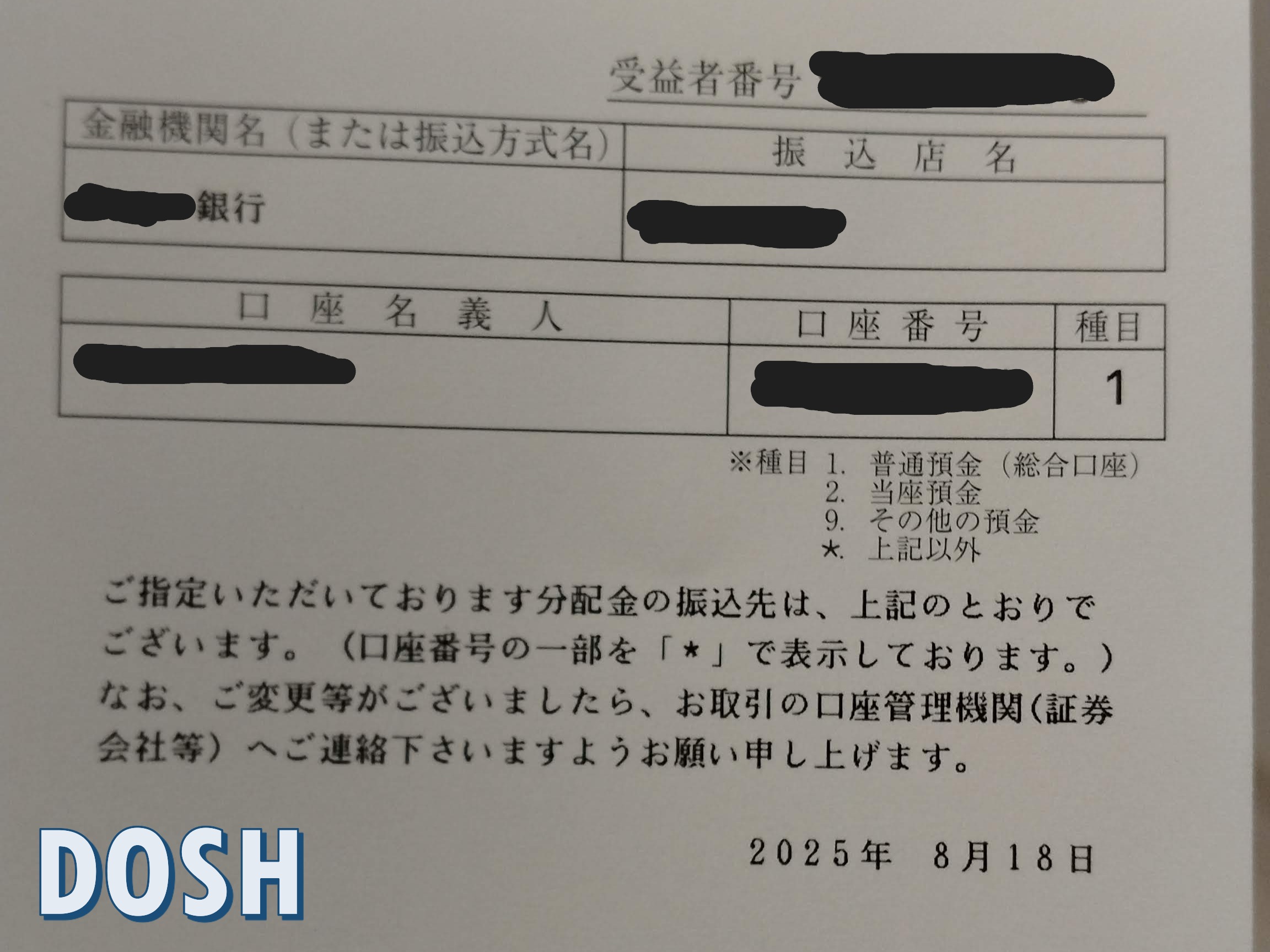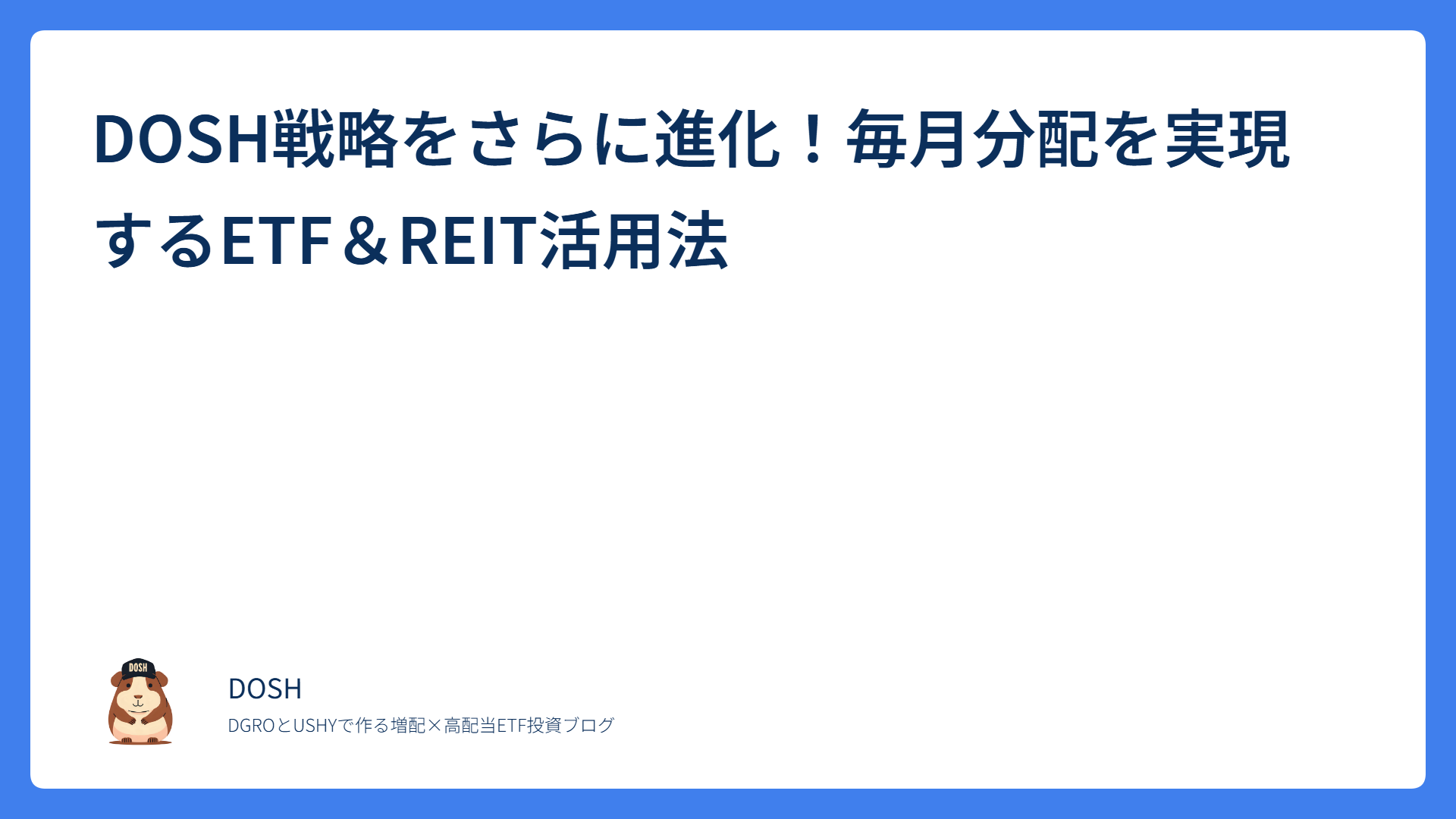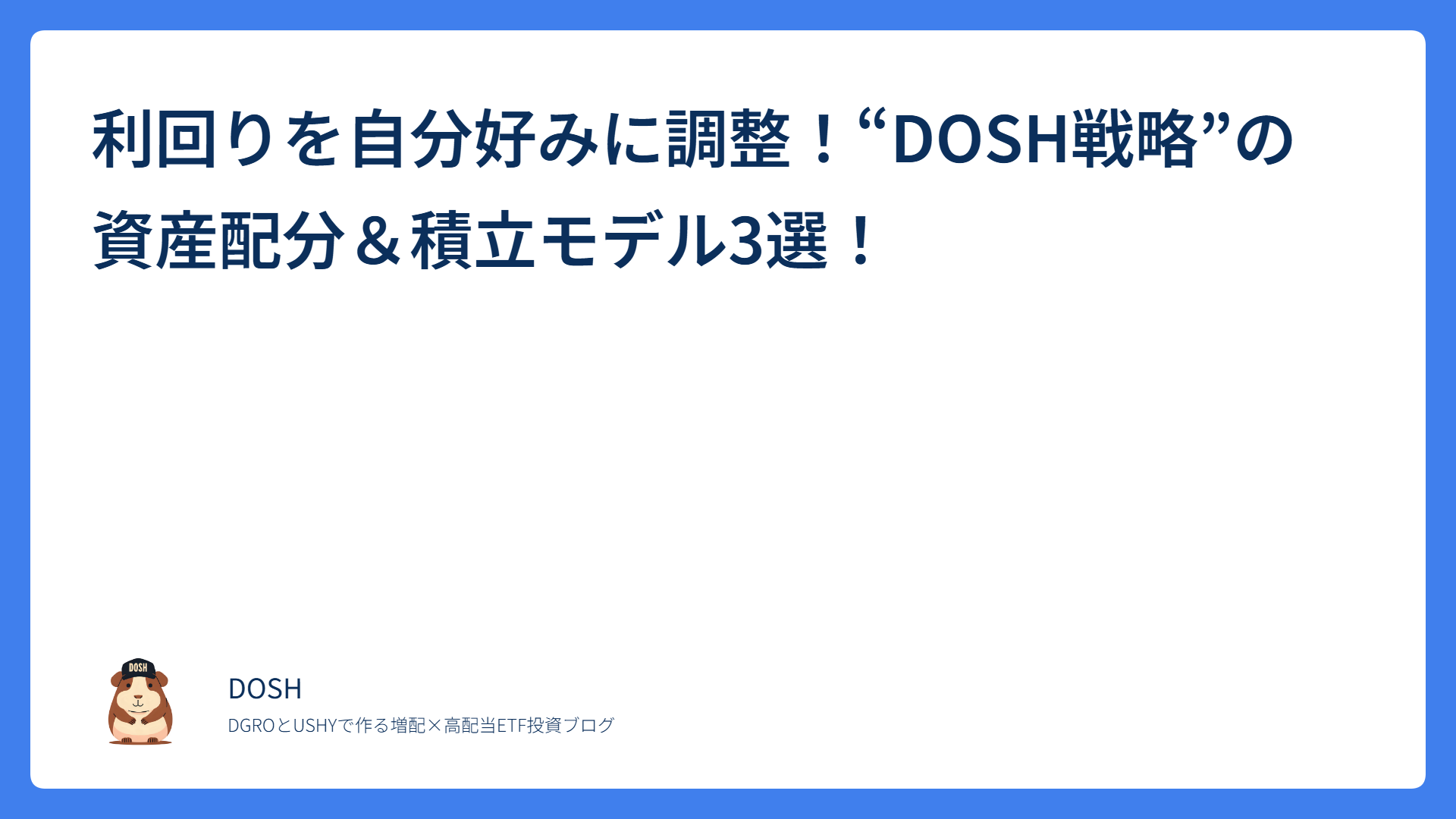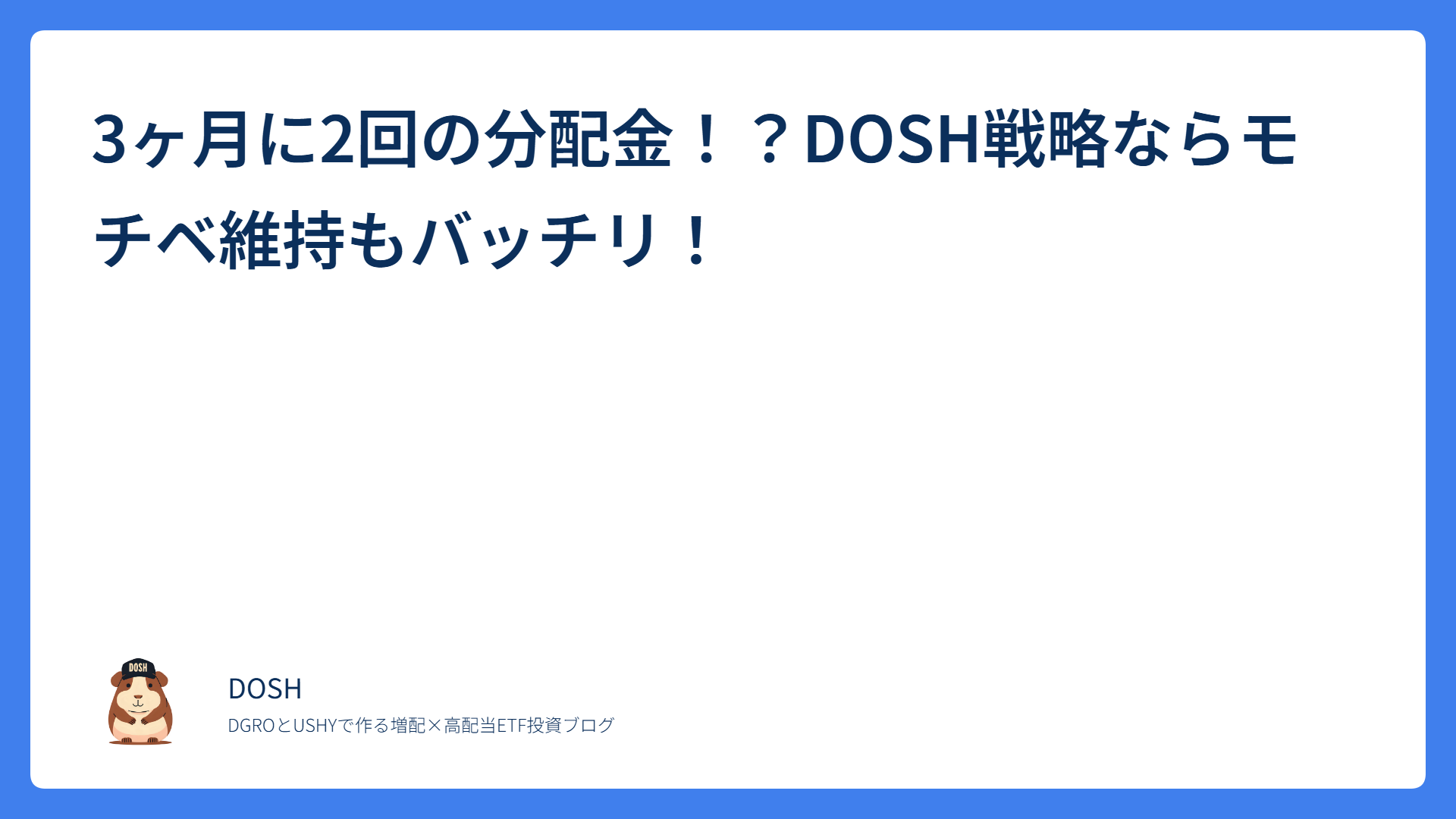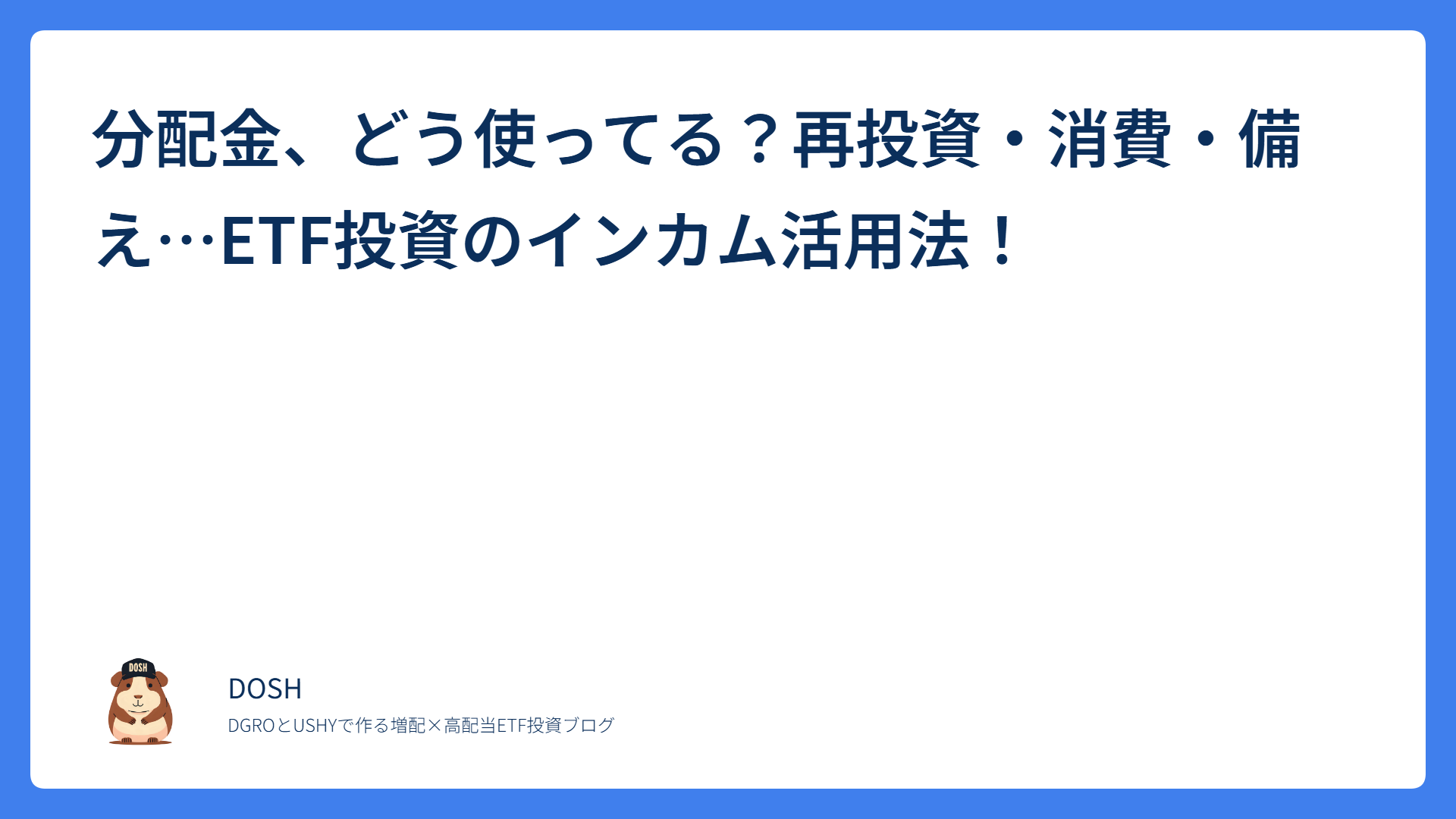DOSH戦略でNISAは使うべき?特定口座と比べたメリット・デメリット
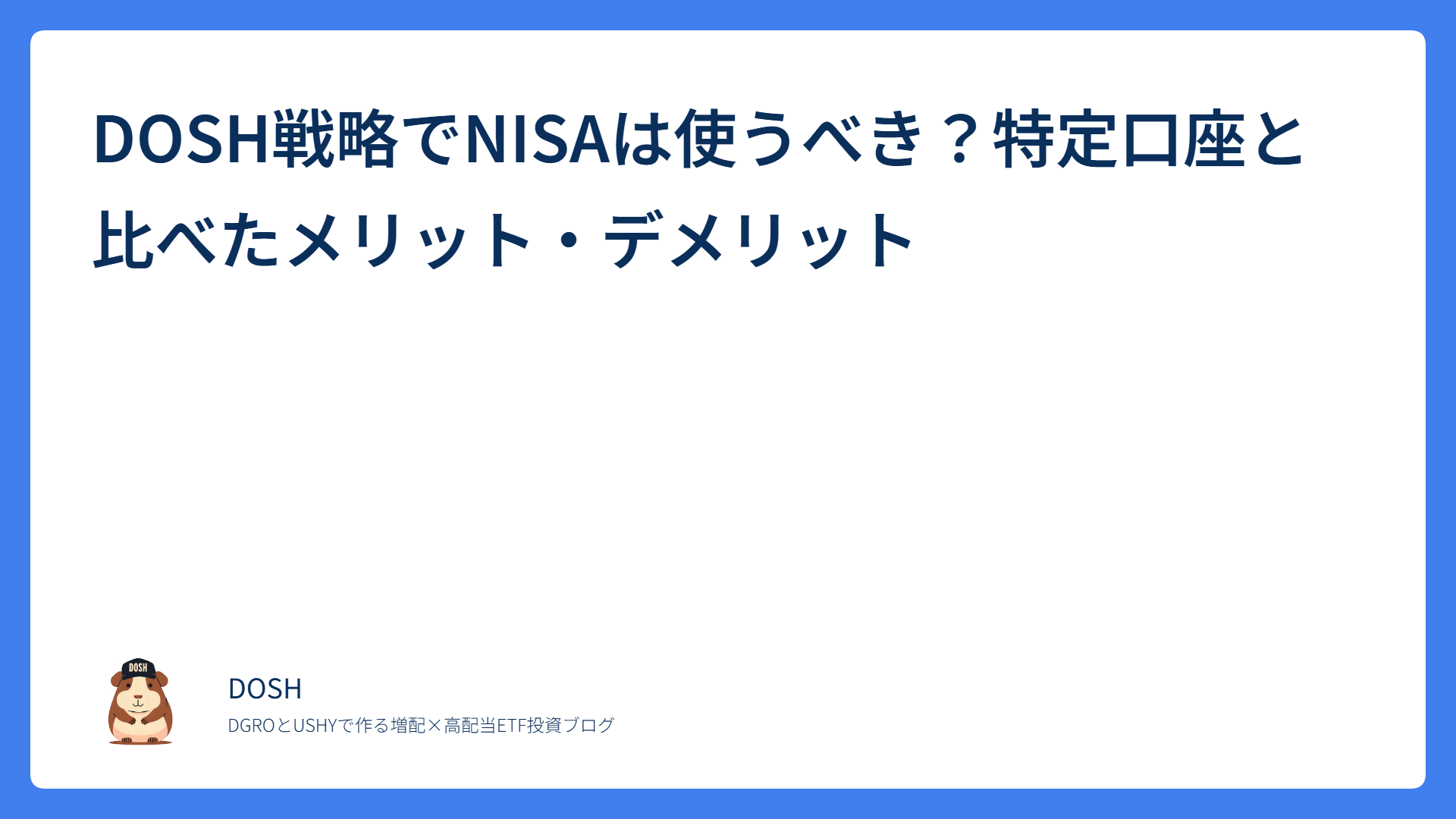
当ブログの独自戦略について
当ブログでは、米国ETF DGRO(増配成長株) と USHY(ハイイールド社債) を組み合わせた「DOSH戦略」を独自に提唱しています!
日本の投資家は直接USHYを買うのが難しいため、東証上場の 2014(DGRO相当) と 2258(USHY相当) を活用すれば、実質的に同じ投資を行うことが可能です。
今回は、そのDOSH戦略を NISAで実践するべきか?特定口座で行うべきか? というテーマを深掘りしていきます。
2014・2258は「積立枠」ではなく「成長投資枠」で買える!
まず大前提。2014と2258はNISAの成長投資枠で購入可能です。
ただし、積立投資枠では買えません。
そのため「成長枠が使えるなら絶対NISAが得では?」と考える方もいるでしょう。
しかし実際には、NISAにも特定口座にもそれぞれメリットとデメリットがあるのです。
NISAでDOSH戦略を使うメリット
最大のメリットはシンプルです。
分配金と売却益が非課税!
これこそがNISAの圧倒的な強みです!
- 通常、配当金や分配金には 20.315% の税金がかかります。
- 例えば、利回り 4% のETFを100万円持っていた場合:
- 特定口座:税引後 約3.2%(年間3.2万円)
- NISA口座:満額4%(年間4万円)
税金の有無だけで「年間8,000円」の差がつきます。
この差は年数を重ねるほど大きくなり、配当再投資を続けると複利効果でさらに広がります!
DOSH戦略は「配当を受け取ること自体」が醍醐味なので、非課税で満額もらえるインパクトは計り知れません。
NISAで使うデメリット
ではなぜ「NISA一択!」とならないのでしょうか?
- 分配金再投資でNISA枠を消費する
→ 分配金を同じ銘柄に再投資すると、その都度NISA枠を使います。
これが意外と煩雑で、「枠を圧迫してしまう」という悩みにつながります。 - 二重課税調整の恩恵がない
→ NISAは国内課税ゼロになる代わりに、米国源泉徴収(約10%)は戻りません。
特定口座なら二重課税調整で取り戻せる分が、NISAでは取り戻せない点は注意。 - NISA枠の優先順位の問題
→ 成長投資枠はとても貴重です。多くの人にとって「S&P500」や「全世界株」のようなインデックス投資を優先したいはず。
DOSH戦略にNISA枠を割り振るかどうかは、他の投資方針との兼ね合いになります。
管理人は特定口座派!その理由
私はDOSH戦略を 特定口座 で実践しています。
その理由は…
- NISA枠はインデックス投資に集中したい!
- 分配金をどう使うか自由にしたい!
→ 再投資でも生活費でも、その時の気分で決めたい。NISAだとそのたびに枠を気にして管理が煩雑になるのが嫌だからです。 - 売却益は重視していない!
→ DOSH戦略は「長期保有で配当を受け取り続ける」ことが前提。NISAの売却益非課税メリットを最大限に活かせません。
つまり、私のスタイルでは「NISA枠はシンプルに成長株インデックス、DOSHは特定口座でインカム重視」にするほうが管理しやすいのです。
NISA派が向いているケース
一方で、NISAでDOSH戦略を実践するのが合っている人もいます。
- 成長投資枠に余裕がある
- 分配金を同じETFに再投資せず、自由に使うつもり
- とにかく非課税で満額の配当を受け取りたい!
こうした方には、NISAでDOSH戦略を組むメリットは非常に大きいです。
まとめ:どちらも正解!
- NISA:分配金・売却益が非課税!→利回りをフルで享受できる
- 特定口座:管理がラク!二重課税調整あり!→枠を気にせず自由に運用できる
DOSH戦略は、NISAでも特定口座でも有効に機能します。
大事なのは「自分が投資で何を重視するか」です。
管理人は 「NISAは成長投資、特定口座はインカム戦略」 で住み分けていますが、これは一つの選択肢にすぎません。
ぜひ、自分のスタイルに合わせてベストな口座を選んでみてください!